月経困難症
月経困難症に対する鍼灸治療
月経困難症とは、日常生活に支障が出てしまう月経痛の事を言います。
月経痛(生理痛)はあって当たり前。そう思っていませんか?
東洋医学では、月経痛や月経周期に伴った不快な症状がないことが正常なのだ、と考えています。毎月ひどい痛みと不快を感じる月経困難症は2つに分類されています。
機能性月経困難症
原因がわからない強い月経痛のことを言います。
器質性月経困難症
原因となる病気がわかっている月経痛のことを言い、病名としては、子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症、骨盤内うっ血症候群、骨盤内感染症などの疾患が挙げられます。
月経困難症の2タイプに共通すること
月経困難症は骨盤内の血液循環が悪くなって、うっ血しているために起こるケースと、ストレスが原因で起こるケースがあります。血流循環を改善する運動やストレス対策は症状緩和に効果的だと言われています。
鍼灸による効果が医学的にも認められている
「科学的な根拠=EBM」をご存知でしょうか。治療が有効である事を調べるための試験、ランダム比較試験(RCT)というものがあります。詳細は省きますが、薬の効果を調べるのに例えると、
- Aグループは本当の薬を服用する
- Bグループは薬効のない薬を服用する
- Cグループは何も服用しない
AとBのグループには、処方する医師も、処方を受ける患者も、誰がどのグループに属しているか、薬が本物なのか偽者なのかわからない状態で受けてもらいます。そして3つのグループの結果を比較することで、薬本来の薬効が調べられるというものです。
それらのRCT論文を集めてより普遍性の高いデータにしたものが、システマティック・レビュー(SR)と言いますが、世界で最も信頼性の高いSRを発表しデータベース化している機関、コクランライブラリに、鍼灸による「月経困難症」に対する効果が認められているのです。
つまり、月経困難症に対する鍼灸治療は医学的に認められており、安心してお受け頂けます。
受診を迷っている方、当院の症例、治療計画の一例をご覧になってからご決断ください。
30代前半Iさん 子宮内膜症
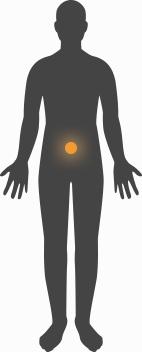
- 主な症状
- 生理痛・肩凝り
- 現病歴
- 子宮腺筋症(手術2回)
- 治療経過
-
<初診>
- 子宮腺筋症の薬物治療をしているが、休薬中1週間の生理様出血時にうずくまる程の下腹部痛と頭痛がある。その他肩凝りと下肢の冷えが慢性的にある状態。
- 初診から1ヵ月間は週1回治療し、その後2週に1回に治療を継続。現在は薬物治療(内膜症の)と鍼灸を併用し、腹痛・頭痛も痛み止めを服薬することもあまりなく生活できている。

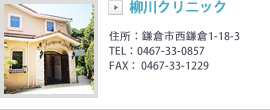
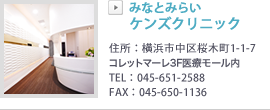
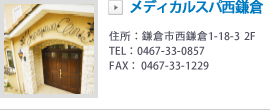
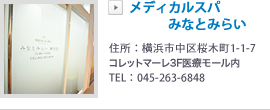
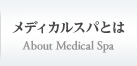

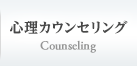



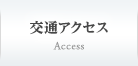






担当施術者の考察
子宮腺筋症や子宮内膜症は、東洋医学では瘀血(おけつ)という冷えなどで循環が悪い状態が続いていると起こる病態と考えています。全身のめぐりをよくすることが結果として痛みの軽減に繋がり、痛み止めの服薬を減らすことができた症例です。
生理痛はあるのだけど、増えがちな鎮痛剤の頻度を減らし、生活の質を下げることなく日常を送りたいと思っている方は一度ご連絡ください。
鍼灸はあなたの婦人科症状のサポートができる医療です。